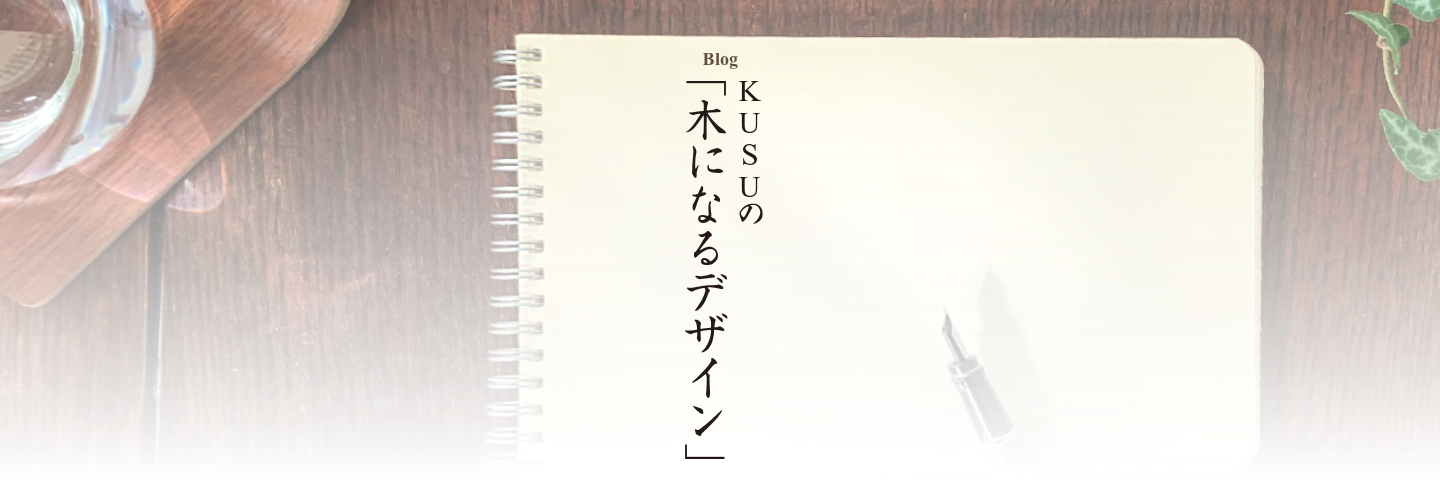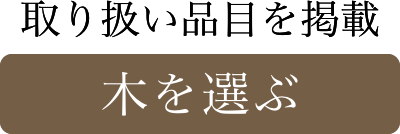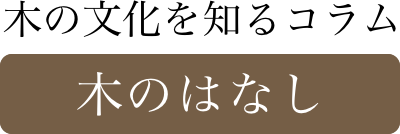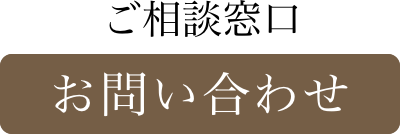和太鼓は日本のリズムを司る
和太鼓は、日本で古代から神社仏閣における儀式などに使用されてきました。芸能分野では田楽や猿楽、神楽や民俗芸能、さらに中世以降は雅楽や能楽、歌舞伎、念仏踊りなどの打楽器として用いられてきました。
代表的な和太鼓の構造は、くりぬき胴か弧形の側板を箍(たが)で締めた結桶構造です。
輪切りにした木材の内部をくり抜いて胴にする長胴太鼓の原木にはケヤキやクスノキなどの紅葉樹を用います。ただし、国産は原料不足のためシオジ・センが主流。また海外からはカリン・ナラなどの堅い木材を用います。
牛の皮(メスは絹、オスまたはホルスタインは木綿に例える)を鋲や紐、ターンバックルや金具等で張りとめてつくられ、桴(ばち)と呼ばれる木の棒で皮を叩いて演奏される。
今では海外でも人気があり、「DRUM TAO」「倭-YAMATO」「彩」などの和太鼓グループが世界で活躍しています。
和太鼓の音色と響きが、日本の伝統的なリズムを司ってきたといえるでしょう。
木に関する様々な情報を発信しています。ぜひ下記ページもご覧ください。 「木のコンシェルジュ」として木に関するご相談にもお応えします。