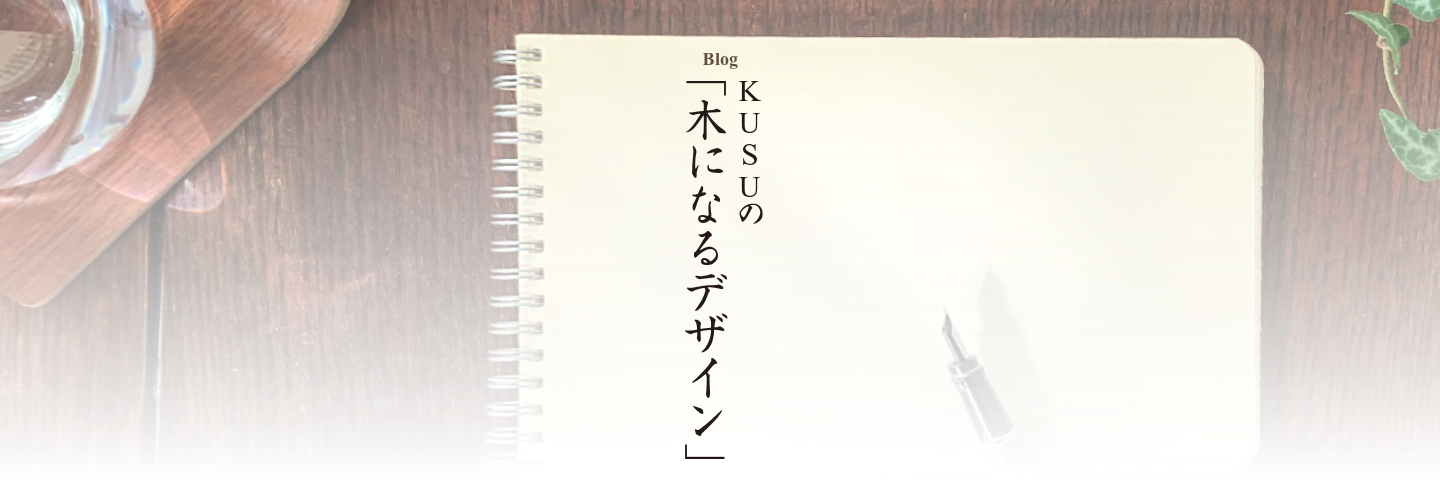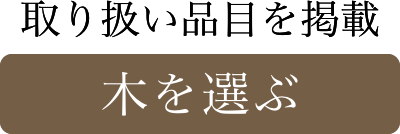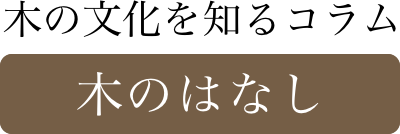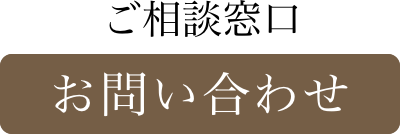組子細工は職人の繊細な技術が生み出す工芸品
組子細工は、細い木材を組み合わせて、幾何学模様を作り出す日本の伝統的な木工技術です。主に障子や欄間などの建具に使用され、繊細で美しい文様が特徴です。
組子細工は、約1400年前の仏教伝来とともに、寺院建築に必要な技術として日本に伝わったとされています。その後、繊細な日本人の感性によって様々な模様が考案され、現代まで受け継がれてきました。
組子細工の特徴は、釘や金具を一切使わず、木材同士を組み合わせて模様を作り出す点です。細かく加工された木材を職人の手作業で組み付けることで、精緻な模様を生み出します。使用する木材は、主にヒノキや杉、ヒバなどの針葉樹で、木目の詰まったものが選ばれます。
近年では、組子細工の技術を生かしたモダンな照明器具やインテリア雑貨なども開発され、その魅力はますます広がっています。
木に関する様々な情報を発信しています。ぜひ下記ページもご覧ください。 「木のコンシェルジュ」として木に関するご相談にもお応えします。